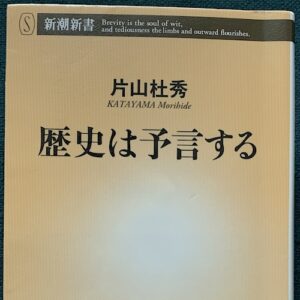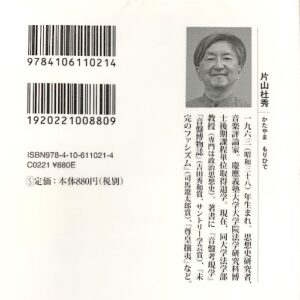音楽とは人の魂に素朴に触れるのがいい。小さくて簡潔なのがいい。贅肉は殺げるだけ殺ごう。 『歴史は予言する』片山杜夫
それが、作曲家・信時潔(1887-1965)の信条で有り、神父の子としてプロテスタントの讃美歌で育った者の「理想の音楽」であったと著者・片山は考えた。
信時について調べれば、東京音楽学校本科の作曲部の創設に尽力し、本科作曲部新設と同時に、自身は教授を辞し講師となったとWeb『信時潔研究ガイド』に書かれていた。
『歴史は予言する』(表紙部分)
『歴史は予言する』(裏表紙部分)
『歴史は予言する』は、週刊新潮連載の「夏裘冬扇」をまとめた一冊。引用部分は、2023/04/20付の初出タイトル「”キメラ”としての坂本龍一」より。
片山杜夫は、”教授の系譜”として、音楽家・坂本龍一の師系を並べ教示してくれた。信時潔(のぶとき きよし)――>下総皖一(しもふさ かんいち)――>松本民之助(まつもと たみのすけ)――>坂本龍一、であると。
ところが、信時も下総も交響曲やオペラも作らず、『海ゆかば』や『たなばたさま』のようなシンプルな歌が彼らの真の代表作だったと。
つまり、現代音楽のシェーンベルクやメシアンの十二音技法(セリー技法、主音がなく平均律の半音階12音をすべて平等に扱う)では考えられないような話だが、日本の民謡や伝統音楽は五つの音から成る音階が基本になっているものが多い。
ピアノを鳴らせば分かりやすいのだが、西洋音楽では、長音階(ドレミファソラシ)や短音階(ラシドレミファソ#)といった七つの音から成る「七音音階」が基本なのに対して、明治維新までの日本音楽では、民謡音階(レミソラド)、律音階(レファソラド)、都節音階(レミ♭ソラシ♭)、琉球音階(レファ#ソラド#)などのように、「五音音階」が基本になっていたと言われている。
たとえば、「ドレミファソラシ」の音に「一二三四五六七」を対応させ、「ヒフミヨイムナ」と数えた時、「ファ・シ」すなわち「ヨ・ナ」の音が無かった日本独自の「ヨナ抜き音階」の世界が現れる。
シンガーソングライターの谷村新司が作詞、作曲した『昴』(1980年)にも、偶然この「ヨナ抜き音階」が使われてヒットしたと聞いたことがある。それだけ、日本人にとっては違和感なく受け入れられやすい音階だともいえよう。
現代音楽の十二音技法は、理論的には面白くても、やはり「人の魂に素朴に触れる」音楽として、私たちの耳にはまだまだ聞こえないのかもしれない。
書 名:歴史は予言する
著者:片山杜秀
発 行:2023年(R5) 12月20日
発行所:新潮社(新潮新書1021)