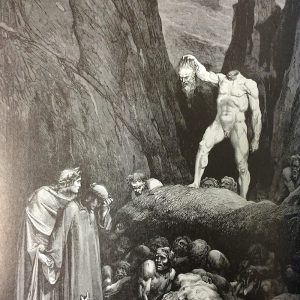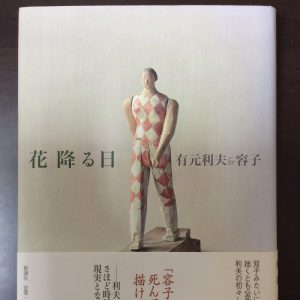WordPress(ワードプレス)は、オープンソースのブログソフトウェアである。
PHPで開発されており、データベース管理システムとしてMySQLを利用している。
単なるブログではなくCMSとしてもしばしば利用されている。
b2/cafelogというソフトウェアのフォーク(後継)として開発、2003年5月27日に初版がリリースされた。
GNU General Public License(GPL)の下で配布されている。
主な特徴
◎ PHPによる動的なページ生成
◎ 標準添付のテンプレート等がウェブ標準に準拠
◎ 記事への複数カテゴリー設定に対応
◎ カスタマイズ可能で検索エンジンフレンドリーなURL
◎ テーマによる簡単なデザインの切り替え
◎ プラグインによる拡張機能
◎ WYSIWYGによるエントリ編集
◎ 投稿スラッグによるパーマリンクURL作成
現在の最新版 Ver.4.2.2 (2015年5月22日現在)