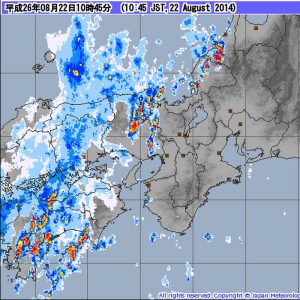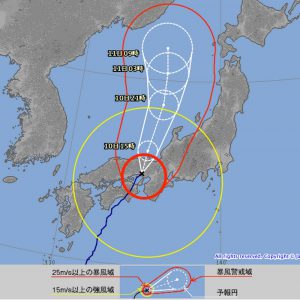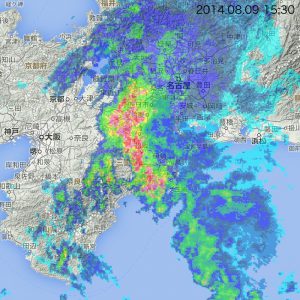瀧の上に水現れて落ちにけり 後藤夜半
句集『翠黛』三省堂
共同通信(2014.08.11)によれば、「東京大と慶応大の共同研究チームが、1兆分の1秒よりも短い時間ごとの連写撮影ができる世界最高速のカメラを開発した」とのこと。
つまり、1兆分の1秒(1ピコ秒)の世界を画像にして、物質の生成や変化を確かめることができるようになったとも解釈できる。
宇宙の彼方の物質は、分光学や電磁波を利用して「観る」すなわち観測できるようになった。そして、分子レベルから原子レベルへと、視野は広がり、深まりつつある。
これまでも高速度カメラを用いれば、水の流れを止めたり、その瞬間、瞬間を描画できたのだが、水の分子より挙動の不安定な水素分子まで観測することができるに違いない。
さて、高浜虚子編の『季寄せ』や稲畑汀子編の『ホトトギス新歳時記』から「滝」の例句を繙けば、まず出て来るのが後藤夜半の「瀧の上に」である。
虚子や山本健吉の批評によって、すっかり名句と知れ渡り、現代俳句に詳しい俳人なら、「瀧の上に」の俳句を知らないはずはなかろう。
人間の目で滝を見て、その後、もっと「観る」、あるいは「視る」ことに心を砕けば、確かにそこに、これまでとは一味も二味も違った世界が顕現してくることに気付くはずである。
たとえば、テレビ番組などで、超能力者による「透視」事例を紹介するものがあるが、あれほどの能力は無くとも、一般人でも、誰でも、何かを見た時に、もう少し、そのもの事態を観察する気持ちで見ることに心を砕けば、今までとは違った何かが視えてくるのではなかろうか。
「よくみる」こと。そして、何かを心に停めること。
これができそうで、中々できない。たった一つのことなら、覚えてもおけるのだが、自分の毎日の生活の中で、あらゆる場面に応用しようとすると、至難の業になる。
そこで、一日に一つから二つ、二つから三つと、増やしていくのが最前の方法とも考えた。
目の前を通り過ぎる物体を、「あ、トンボ」から、「あ、オニヤンマ」、「あ、胴体に、忘れな草の花のような色のあるオニヤンマ」、「あ、胴体の一部に鮮やかな勿忘草色、眼は半透明の緑青色のクロスジギンヤンマ(黒条銀蜻蛉)」と。
実は、そこから、もう一歩踏み出して、視ることができれば申し分ない。
虚子の「客観写生」のその向こうには、何が視えたのだろう。
蜻蛉のさらさら流れ止まらず 高濱虚子
とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな 中村汀女
芭蕉は、「物の見えたるひかり、いまだ消えざる中に云ひ止むべし(三冊子)」と言っている。
トンボは物である。太陽の光を受け、昆虫の外骨格や羽が可視光線を反射して、人間の網膜にトンボの動くカタチとして映し出される。網膜や脳細胞のシナプスからその映像が消える前に、私たちは感じた何かを言葉に変え、記憶していく。映像だけより、言葉に変えて同時に蓄積しておくほうが、記憶力は何倍も増すだろう。
俳人は、「蜻蛉(とんぼ)」と聞いただけで、季語の蜻蛉を思い、蜻蛉のいくつかの例句とその情景、自分の過去の蓄積映像や画像を頭の中で反芻している。
作句歴が長ければ、自分の作った蜻蛉の句も思い出し、より鮮明に作句時の映像が浮かんできているかもしれない。
それだからこそ、物のその向こうに光るナニモノかを捉え、自分に納得できるモノや感覚として一度は掴んでおきたいと思う。
毎日見過ごしそうな物達を、一瞬でも力を入れて視る、あるいは「捨て眼」として、その時は必要とせずとも、後から記憶の糸をたどって思い出せる映像として、心ふるわせ、どこかに仕舞っておきたいと思う。
参考:
後藤夜半(Wikipedia)「滝の上に水現れて落ちにけり」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E5%A4%9C%E5%8D%8A
『日本新名勝俳句 : 懸賞募集』大阪毎日新聞社[ほか]